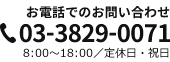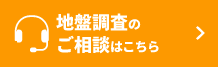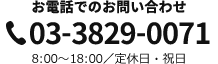法隆寺五重塔
法隆寺の制耐震技術の脅威
柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺
世界最古の木造建築物である法隆寺は仏教布教のため聖徳太子によって608年建立された。「大化の改新」では仏教興隆の恩人である蘇我氏が滅ぼされた。670年落雷にて消失。すぐに再建された。1600~1606年慶長大修理、1692~1707年桂昌院による大修理、明治時代の{廃仏毀釈}では回廊内に牛馬を繋がれる状況に陥った。昭和の大修理(1933~1953年)で当初に近い復元ができた。様々な政変を乗り越えさせた原動力は日本人の「聖徳太子」信仰が法隆寺を守り続けたかのようだ。
法隆寺を支える地盤について
法隆寺はマグニチュード7.0以上の地震を46回も経験し、乗り切ってきた。その最大の要因は、地形地質である。この地域は砂礫質台地と呼ばれる地形で、隆起によって生じた段丘を形成し、表層に約5m以上の砂礫層、砂質土層を持つ安定した地盤。つまり揺れにくく、液状化しない場所を選定したことになる。建設担当者に地盤や基礎に対する経験と知識があったことは間違いない。
日本独自の建築技術「心柱」の確立
第一は、日本は雨の多い国で中国の年間降雨量の約2倍だ。このため、雨水が建物から流れ落ち、土台周辺の土壌に降り注ぐと、五重塔がいずれ沈んでしまいかねない。これを防ぐために、大工たちは、庇を壁からかなり離して長く造った。建物の全幅の50%以上にもなる軒だ。この巨大に張り出した部分を支えるために、片持ち梁を庇ごとに採用している。
第二は、建造物の著しい燃えやすさへの対抗策として、庇には瓦が積まれ、木造建築物に火が燃え広がらないようになっている。
第三は、法隆寺の五重塔は、現代建築に見られるような、中央の耐力柱がない。上に行くほど細くなっていく構造のため、耐力垂直柱で繋げている部分は一つもない。 各階が強固に繋がっているわけではなく、ただ単純に重ねたところを取り付け具でゆるく留めているのみなのだ。この構造は実際、地震国では大変な強みになる。地震の際、上下に重なり合った各階がお互いに逆方向にくねくねと横揺れするため、強固な建物にありがちな揺れ方はせず、振動の波に乗った液体のような動きになる。
第四に、一方で、あまりにも各階が柔軟になりすぎるのを避けるために、大工たちは、とある独創的な解決法に行き着いた。これが心柱だ。見た目は、大きな耐力柱のようだが、実際にはこれは建物の重さをまったく支えていない。心柱は、まさに自由な状態で吊り下げられているだけなのだ。心柱は、大型の同調質量ダンパーの役割となって、地震の揺れを軽減する助けとなっている。各階の床が心柱にぶつかることで、崩壊するほどの横揺れを防ぎ、揺れもいくらか吸収している。言うなれば、基本的には、十分な質量のある不動の振り子であり、より軽い各階の床があまりに自由に横揺れしすぎないように歯止めをかけている。
現在でも、これと同じダンパー技術が使われているスカイツリーのほかに台北101(台北国際金融センター)は、92階から巨大な、730トン4階分の鋼鉄の振り子をぶら下げ、強風でビルが横揺れするのを防いでいる。ニューヨークのシティコープ・センターもまた、ハリケーンの際の揺れを防ぐのに、400トンのコンクリート・ブロックを使用している。
教科書から消える聖徳太子 歴史が英雄をつくる! 聖徳太子的人物の存在が・・・
 聖徳太子から福沢諭吉へ
聖徳太子から福沢諭吉へ
聖徳太子の業績は、冠位十二階、憲法十七条、遣隋使派遣などが上げられますが、歴史研究の発展により、実はこれらは、太子一人の実績ではないことが明らかになってきたようです。そこで教科書では、聖徳太子の表記を止め、厩戸王と表記するようになったようです。しかし、この時代の天皇の摂政として存在していたのは確かなようですが1万円札の肖像としての復帰は難しいかも知れません。
仏教による国づくりの象徴としての聖徳太子
当時の日本が国づくりを進める中で、大陸の宗教や立法、身分制度を参考にしたのは間違いない。しかし、それは自然に入ってくるものではなく、明確な目的意識と行動を必要としたはずだ。それを取り入れた英雄こそ、聖徳太子的な人物だったのではないだろうか?(もし、ナポレオンが生まれてこなかったら、歴史は別のナポレオンを生み出した)
大工の神様 聖徳太子
11月22日は「大工さんの日」です。11月が「技能尊重月間」、十一を合せると「建築士」の「士」の字になること。22日が聖徳太子の命日(622年2月22日)さらに11は二本の柱、二は土台と梁と見なして「大工さんの日」としたようです。 孟子の教えに「規矩準縄(きくじゅんじょう)」という言葉があります。物事や行動の基準、手本を正しくすることを意味するとのこと。 ここから発して大工の伝統技術に規矩術(きくじゅつ)というものがあり、大工の数学のようなもので、「規」とは「円を描く」、「矩」とは「方向、直角」、「準」とは「水平」、「縄」とは「垂直、鉛直」ということを意味し、家造りの最も基本となるキーワードです。更に、大工道具のことも指しているそうで、『規=定規』『矩=差し金』『準=水盛り』『縄=墨縄』となります。 この中の『矩=差し金』を日本に持ち込んだのが聖徳太子とのことです。 法隆寺のような建造物を初めて日本に作るためには、道具と技術の伝承は絶対的に必要だったことは間違いない。 道具は現物でよいが、技術はどうしたのか?聖徳太子は太子講といって、大工を集めて建築の講義のようなものをしていたそうです。 当時の政治家はテクノロジーの優れた伝承者でもあったようです。