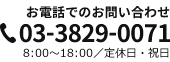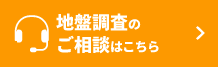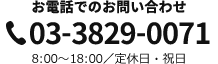2018年3月15日発行 地質時代第18号 1面
目に見えない財産
3月11日、東日本大震災から7年目を迎え、ニュースで沢山の特集が組まれた。家は復旧できても、目に見えない『ご近所付合い』の絆がなくなったことへの喪失感ははかりしれない。人は家がなくても生きていけるが、共同体がなくなると生きていけない生き物なのだろう。今後、日本は「首都直下型地震」はじめ各地で巨大地震が確実に起こると見られている。そのためのハードな防災対策の必要性は当然ですが、復興にあたり地域の人間関係という目に見えない財産を守ることも一体に考える必要があります。
『方丈記』の世界観

長明が隠遁した方丈(3m四方)のあばら家の復元 下鴨神社」
『方丈記』は1212年頃、鴨長明によって完成された随筆集ですが、平安時代末期から鎌倉時代初期の出来事が取り上げられている。その内容は、当時の災害と人間の記録でもあった。 「ゆく川の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」 このフレーズは、どこかで聞いたことがある。『方丈記』は都を襲った「安元の大火」1177年、「治承の辻風(竜巻)」1180年、福原遷都による混乱(1180年)、養和の大飢饉(1181年から82年)、元暦の大地震(1185年)の数々の災難を経験した長明がこの世の無情を著した。その歴史的背景には、貴族社会から武家社会にむけた混乱とそれを宗教的に結びつけた「末法思想」があった。 ゆく川の流れは絶えることがなく、しかもその水は前に見たもとの水ではない。玉を敷きつめたような都の中で、棟を並べ、屋根の高さを競っている、身分の高い人や低い人の住まいは、時代を経てもなくならないもののようだが、これはほんとうかと調べてみると、昔からあったままの家はむしろ稀だ。あるものは去年焼けて今年作ったものだ。またあるものは大きな家が衰えて、小さな家となっている。朝にどこかでだれかが死ぬかと思えば、夕方にはどこかでだれかが生まれるというこの世のすがたは、ちょうど水の泡とよく似ている。一時の仮の宿に過ぎない家を、だれのために苦労して造り、何のために目先を楽しませて飾るのか。その主人と住まいとが、無常の運命を争っているかのように滅びていくさまは、いわば朝顔の花と、その花につく露との関係と変わらない。あるときは露が落ちてしまっても花は咲き残る。残るといっても朝日のころには枯れてしまう。あるときは花が先にしぼんで露はなお消えないでいる。消えないといっても夕方を待つことはない。
無常への絶望か、価値観の転換か
鴨長明の時代と現代は結構似ている。栄華を誇った東芝の挫折、「官庁の中の官庁」財務局の文書改ざんなど政治は乱れ、企業の生産第一主義はいたるところで破綻、人々の協力と共同による心の豊かさを求める時代を求め動いている。 災害が突きつける被害や傷は、流れる川のように避けることはできない。豪華な家が時と共に必ず廃れていくようなものだ。物質的な豊かさは儚く、頼りにならない。本当に価値あるものは、人と人とのつながり、栄華を競い合うのではなく貧しくても、共に助け合う心の豊かさこそ本当に価値あるものだ、と教えているように思う。